「陰摩羅鬼の瑕」を読みながら、ふと
つい先日まで、『ジョジョ』のスピンオフ小説『無限の王』を読んでいたのですが、ここ最近は僕が憧れる京極夏彦先生の『陰摩羅鬼の瑕』を読み進めています。
ご存じ、“百鬼夜行シリーズ”の一つであるこの作品、相変わらず膨大なページ数がまず目を引くのですが、ざっと見たところなんとそのページ数・約1300。
手元にあるのは文庫本なのですが、厚さ4cmになろうかという圧倒的なボリュームで、毎度毎度、手にしたファンを驚かせてくれます。
読んでも読んでもまるで終わりの見えてこないこの独特の感覚も、“百鬼夜行シリーズ”独特、というところでしょうか。
そんな憧れの先生の一冊を手にしながらふと思い返したのですが、思えば随分長い間、僕は京極夏彦先生の著書に魅了され、それを追いかけてきました。
しかし、その“はじまり”はなんだったんだろう――そんなことを思い返した時、きっかけは実に奇妙なものだったのを思い出したのです。
今もなお、憧れの先生として追い求める京極夏彦作品との“出会い”を振り返ってみたいと思います。
きっかけは映画「魍魎の匣」
僕は今でこそ千葉で結婚し、家族を授かることができたのですが、元々は岡山の片田舎に生まれ育ちました。
そんななかで、僕の母は大の“ホラー・ミステリ好き”で、そんな彼女の影響を受けてか我が家は僕のみならず弟や妹までも、“ホラー・ミステリ”というジャンルをこよなく愛する人間に育ったのです。
当時はまだAmazonPrimeやNetflixのような、いわゆる“サブスク”というものが流行っていなかった時代、もっぱら映画作品を観るといえば近くのレンタルビデオ屋に家族でおもむき、気になる作品をレンタルして干渉する……というのが常でした。
定期的に気になる作品を供給するのが我が家のルーティーンとなっていたわけですが、そんななかでふと手に取ったのが、当時、実写映画化されていた『魍魎の匣』だったのです。
しかし、当初我々は京極夏彦という作家の存在も知らず、そもそもこの作品が小説を題材にした実写化映画であることも、そもそも『姑獲鳥の夏』が前作として映画化されていたことも、まるで知らないまま「おそらく、ホラーかミステリなのだろう」レベルの、ふわっとした心構えで観てみることに。
まぁ、今思い返すと、「演者に阿部寛もいるしな」という、それくらいの感覚で手に取ったのかもしれませんね。
よく分からない…で、終わりたくない一心で手に取った原作
予備知識ゼロの状態で映画『魍魎の匣』を観てみた我々家族一同でしたが、正直なところ、この段階では映画の内容がまるで理解できず、率直に言えば「よく分からない」という感想を抱かざるをえませんでした。
元々、“百鬼夜行シリーズ”の一編を描いた作品でありながら、僕らは「京極堂とは何者か」、「彼の周りの人物はどういう関係なのか」といった前提も知らないわけですし、数時間の映画の中ではそういった前提条件が十分に語り切れていない部分も多く、初心者にとってはあまりにも難解な映画といわざるをえなかったのです。
その時点では映画としてはどこかがっかりな判定を下していた我が家なのですが、それでいて僕の中には「このまま、『よく分からない』で終わりたくない」という、妙な意地が残っており、後々になって改めて『魍魎の匣』とはなにか……を、調べてみることにしました。
ここでようやく、僕はこの映画がシリーズ小説の実写化作品であり、そしてそれを書いた人物が京極夏彦という名であるという事実を知るわけです。
ならばと早速、本屋に立ち寄り、まずはシリーズの始まりでもある『姑獲鳥の夏』を手に取ってみるわけですが、まずはそこで本の“分厚さ”に面食らってしまいました。
前述のとおり、そもそも“百鬼夜行シリーズ”は“ブロック本”とも例えられる圧倒的な文章量が特徴で、『姑獲鳥の夏』はまだ全体を通せば短めですが、それでも一般的な小説のそれを圧倒するボリュームで読み手としても初心者の僕を圧倒してしまったのです。
そもそも、毎日読書をするわけでもなければ、多くの文学作品を読んできたわけでもなかった僕ですから、この『姑獲鳥の夏』を読了するにも随分と時間がかかったのを覚えています。
毎日数ページずつ、ときにはその難解な知識や描写に足を止めつつも、僕は着実に“百鬼夜行シリーズ”に立ち向かっていったのです。
一気に引きずり込まれた、京極夏彦作品の“魅力”
正直なところ、今でもこの“百鬼夜行シリーズ”に立ち向かうのはかなりの気合を必要とします。
しかし、どうして毎度毎度、そんな圧倒的な量の文章に手を出すのか――それはやはり、京極夏彦作品が持つ独自の“魅力”を、身をもって体感したからでしょう。
『姑獲鳥の夏』で初めてそれを感じ、『魍魎の匣』、その後に続く様々な作品でも、先生の持つ独自の“魅力”は変わらず、僕を気が付けば読書の沼へと引きずり込みました。
なかなか言語化するのは難しいのですが、先生の作品にはどこか“続きを読みたい”と思ってしまう着火点のようなものがある気がするのです。
最初でこそ、奇怪な事件や現象が発生し、それを主人公たちが巻き込まれながらもどうにかこうにか紐解いていく――という、一般的な“ホラー”や“ミステリ”の流れを汲んでいるのですが、その奥底に眠る“闇”の一端が見えた瞬間、読み手も自然とその世界観に惹きこまれ、「何が起こるのか」を強く見届けたくなってしまうのです。
そして最終的に、そこに隠されたあまりにも予想外の事実――その多くは、我々のような「人間」という生き物が抱く、あまりにも身勝手で、独特で、ときには幼稚で――しかし、とんでもなく“純粋”な犯行動機に、読み手までもが圧倒されてしまう。
劇中の登場人物たちがその真実に狼狽する中、読み手である僕らまでも同様に唖然とし、言葉を失う。
あの渾然一体となった臨場感は、京極先生ならではの強烈な“色”なのだと思う次第です。
読者を引きずり込む、その強烈な“魔力”にあこがれる
改めて原作の『魍魎の匣』を読んでから映画も観てみたのですが、やはり原作に比べると尺の都合上、削られていた表現があったり、大きく流れを変えられていたりと、なかなか映像作品で先生の作品の“魅力”を表現しきるのは難しいのだな、と痛感してしまいました。
しかし、もはや先生の作品が持つ独特の力は、“魅力”などという言葉では到底生温く、読み手を知らず知らずのうちに世界観に同化させ、そして読み終えた後も自分自身の中で何度も考えさせられるような、一種の“魔力”に似た凄まじいものを秘めているように感じます。
無論、先生が手掛けて作品はどれもフィクションではありますが、劇中で起こった事件・出来事を通じ、「僕だったらどうするのだろう」と、最後は考えてしまうところがあるのです。
気が付けば読書を通じ、自分の人生観にすらその波紋が伝わってくる――この感覚は、なかなかほかの小説作品では味わったことがないかもしれません。
小説化を目指し“新人賞”などに応募すると、時折「あなたに影響を与えた作品」というものを書かねばならない時があります
そういったとき、僕はまず迷うことなく、候補の一つに京極夏彦先生の『魍魎の匣』を挙げるのです。
あの時の奇妙極まりない読書体験が、今もなお確かに僕の中に残り、その作風に確実に影響を与えている――僕の今の実力では笑われてしまうでしょうが、それでも僕の憧れは京極夏彦先生であり、読み手の“人生”すら揺らがせるほどの作品を書きたい、と今でも確かに思っています。
きっと、数ある“新人賞”のなかでも、あえて「メフィスト賞」に挑み続けている理由は、京極夏彦先生が創立した賞を、自分も受賞してみたいという憧れがあるのかもしれません。
作家以外にも、様々な分野で活躍する京極夏彦という存在を前に、彼のような“エンターテイナー”になりたいと、今日も今日とて頭をひねり、自分なりの世界を作り上げてく日々です。

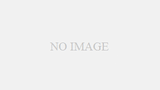
コメント