きっかけはとある新人賞の講評にて
最近も続々と新たな小説作品を書き上げている僕ですが、ここ最近、ずっと思い悩んでいることがあります。
それは、小説というものを書く上での“視点”という概念について。
きっかけとなったのはTwitterことXでバズっていたある記事についてで、とある“新人賞”にて審査員の方が書き込んだある講評が、巷で物議を醸しだしていたのです。
そもそも、その“新人賞”の受賞作が“なし”という状況になったことも大きな話題を呼んだのですが、そこに記された審査員のコメントはまぁ痛烈で、“作家”を目指す人々がその内容に目を通し、様々な意見を上げていました。
そのなかでも特に、小説を書く上での“視点”という概念が強調されていたことから、SNS上では様々な意見が飛び交い、“作家”たちの熱い議論が巻き起こる結果となったのです。
その出来事がきっかけとなり、僕はあれからずっと“視点”というものについて、自分自身のなかで問答を繰り返し続け、いまだにしっくりとくる答えに出会えていません。
誰の“視点”で物語が展開するか
“視点”とは言わずもがな、小説内部の文章が「誰の目から見たものか」ということを表すものなのですが、僕が知る限りでは大きく分けて二つ――「一人称視点」と「三人称視点」が小説の書き方として流通しているように思います。
「一人称視点」とは劇中の登場人物の視点で語られる物語で、例えば“僕”や“私”といった誰かがその物語のなかで体験したことや、見えたもの、感じたことが描かれていくわけですね。
このため、作品が常に特定の誰かにフォーカスを当て続け、あくまでその人物の主観や感情を描いていくことになります。
一方、「三人称視点」はいわゆる“神”の目線で物語が語られていき、常に俯瞰した立場から見た情景を、文章としてつづっていきます。
このため、先程のような“僕”や“私”という表現はほぼ登場せず、常に登場人物の名前と、その人間がなにをして、どう思ったかを説明的に表現していくことになるのです。
僕も小説を書く上ではこの“視点”は気を付けていたつもりですし、基本的には後者の「三人称視点」として物語を展開していっていたつもりです。
ただそれでも、やはりどこかでこの“視点”がずれたり、曖昧になったところがあるのではないか――なかなか自分自身ではしっくりくる答えは導き出せないのですが、それでも過去に書いた様々な作品の“視点”がどうにも気になってしまうようになりました。
とある作品のコメントにも登場した“視点”
そんな疑問を抱きながら執筆を続けていた僕ですが、ありがたいことにちょくちょく、過去に書き上げた作品にコメントもいただいたりします。
ですがそのなかにも、「もっと視点を意識するといいかも」というコメントがあったりと、過去の講評以来、ずっと考え続けていた“視点”の概念がここでも登場することとなりました。
たしかに、過去に執筆し投稿した作品はそういった小説執筆のノウハウをまるで考えなかった作品ばかりなのですが、一方でその頃の文体と現在のそれが大きく進化したのか……と言われると、どうにも疑問が残るのが本音だったり。
“視点”をブレさせないというのが基本であるということが分かっている一方で、とはいえその“視点”を効果的に使うというのは、どういうことなのか。
きっとその正解にたどり着くには、まだまだ僕自身の経験値や勉強量が足りないのかもしれません。
はたして、小説のキモとなる“視点”のあるべき形とは、いかに――きっとこれからも悩み続ける、大きな大きな命題なのかもしれませんね。

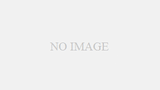
コメント